|
都市計画法の一部を改正する法律
(1)市街化調整区域における地区計画の策定対象地域の拡大等
|
|
良好な居住環境の確保を図りつつ、郊外型住宅の建設の促進、地区の活性化等を図るため、市街化調整区域における地区計画の策定対象地域を拡大し、これまでの大規模計画開発地域だけでなく、小規模な開発を誘導する区域においても策定を促進するとともに、地区計画に適合する行為を開発許可対象に追加する。
|
(2)特別用途地区の多様化
|
|
地域の実情に的確に対応したまちづくりの促進を図るため、用途地域の用途制限を補完する特別用途地区の多様化を行う。
|
|
(現 行)
|
|
(改正後)
|
|
文教地区、特別工業地区等
11類型を法令で限定列挙
|
|
→
|
|
具体的な都市計画で地方公共団
体が多様な目的を柔軟に設定
|
|
|
|
これによって、例えば、以下のような新たな特別用途地区を設定することが可能となる。
◯「中小小売店舗地区」:商業地域等において、商店街を中心に中小商店の集積・展開による街
並みの形成を図るため、中小店舗以外の立地を制限。
◯「特別住居地区」:住居系の地域において、住民の利便の確保と良好な住環境の両立を図るた
め、立地可能施設を限定。
◯「住工共生地区」:準工業地域等において、工場と住居とが調和を図りつつ共存するため、一
定の施設の立地を制限。
◯「高度商業業務集積地区」:工場等の跡地等に大型の商業施設、オフィスビル等を集積させ、
都市の中心としての高度な機能を有する街区を設けるため、これ
らの施設の立地について制限を緩和。
(それぞれの地域の実情に照らして、適切な特別用途地区を設定することが可能。)
|
(3)都市計画における地方分権の推進
|
|
地方分権の推進の観点から、市町村が定める都市計画の範囲を拡大する。
法律改正により、臨港地区(港湾を管理運営するため定める地区)に関する都市計画のうち、
重要港湾に係るものを除き市町村決定とする。
この他に、市町村決定の範囲を拡大するため、広範な政令改正を予定。
|
中心市街地における市街地の整備改善及び
商業等の活性化の一体的推進に関する法律
(1)基本的考え方
1.市町村のイニシアティブ
2.「市街地の整備改善」と「商業等の活性化」が車の両輪
3.「都市化社会」から「都市型社会」への歴史的転換期に当たっての「都市の再構築」
4.個店や商店街に着目した「点」・「線」から、「面」的な商業活性化策へ
5.各省協議会等、関係省庁の連携による各種措置の一体的推進
(2)スキーム(下図を参照)
|
1.国が、「基本方針」を作成
2.市町村が基本方針に即して市街地の整備改善及び商業等の活性化を中核として関連施策を総合的
に実施するための「基本計画」を作成し、国及び都道府県は助言
3.市町村の「基本計画」に則って中小小売商業の高度化を推進する期間(TMO)・民間事業者等
が作成する商店街整備や中核的商業施設整備等に関する事業計画を国が認定し、支援を実施
|
(3)主な支援措置
[市街地の整備改善の推進](建設省)
1.公益施設等の用地を確保するための土地区画整理事業の特例制度の創設
2.路外駐車場に係る都市公演の占用の特例
3.都市開発資金貸付制度の拡充(再開発の種地への低利融資の充実)
4.都市のまちづくり公社等の指定(中心市街地整備推進機構(仮称))
5.地域進行整備公団の業務の特例(土地区画整理事業の施行権能、施設等の整備等)
6.都市計画に基づく事業の推進
[商業・都市型新事業の活性化](通商産業省)(商業施設の整備、TMOを中心とする商店街整備、都市型新事業立地促進)
1.施設整備等への補助、高度化無利子融資等
2.地域振興整備公団による施設整備、3セクへの出資等
3.産業基盤整備基金の債務保証、利子補給等
4.中小企業信用保険の特例(不保限度額の拡大、保険料率の引き下げ等)
5.中小企業設備近代化資金の特例(償還期間を7年に延長)
6.課税の特例(特別償却等)
[その他]
1.地方税の不均一課税を行った場合の地方自治体の減収補填(自治省)
2.地方債についての配慮(自治省)
3.食品商業集積施設の整備の促進(農林水産省)
4.旅客・貨物運送事業の円滑化のための許認可手続きの特例(運輸省)
5.電気通信基盤施設の整備の促進(郵政省)
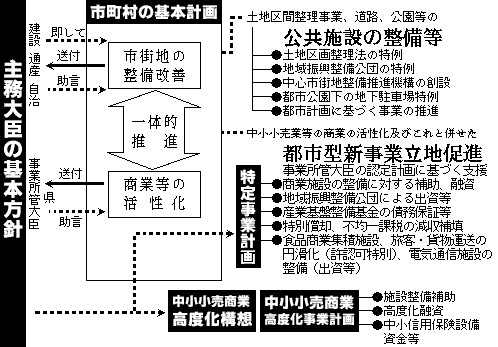
【HOME】 【前目次】
|